2025.10.28
筋トレがきつい時の対処法と継続のコツ|無理なく続ける方法

筋トレを始めてみたものの、「きつい」「続けられない」と感じているのではないでしょうか。実は、筋トレがきついと感じるのは誰もが通る道であり、その理由を理解して適切に対処することで、無理なく継続できるようになります。
本記事では、筋トレがきついと感じる理由から、その対処法、継続のコツまで詳しく解説します。トレーニングの強度調整や休息の取り方、モチベーション維持の方法など、実践的な内容をお伝えしていきます。
筋トレがきついと感じる5つの理由
筋トレがきついと感じる背景には、いくつかの共通した理由があります。これらを理解することで、自分に合った対処法を見つけやすくなります。
運動強度が体力に合っていない
筋トレを始めたばかりの方によく見られるのが、自分の体力レベルを超えた強度でトレーニングを行ってしまうケースです。SNSや動画で見た内容をそのまま真似したり、周りの人と同じメニューをこなそうとしたりして、体に過度な負担がかかってしまいます。
運動経験や現在の体力レベルは人それぞれ異なります。例えば、普段運動をしていない方がいきなり重いウェイトを扱ったり、長時間のトレーニングを行ったりすると、体が対応できずに「きつい」と感じるのは当然です。トレーニングは段階的に強度を上げていくのが望ましく、まずは自分の体力に合った負荷から始めましょう。
適切な強度の目安としては、「ややきつい」と感じる程度がよいとされています。会話ができないほど息が上がってしまうときは、強度が高すぎるかもしれません。一方で、まったく疲れを感じない場合は、強度が低すぎる可能性があります。自分の体の声に耳を傾けながら、適切な強度を見つけていきましょう。
休息期間が不十分
筋肉は、トレーニングによって微細な損傷を受け、その後の休息期間中に修復されることで発達していきます。この修復プロセスには時間が必要であり、十分な休息を取らずに次のトレーニングを行うと、疲労が蓄積してしまいます。
特に初心者の方は、早く変化を出したいという気持ちから、毎日トレーニングを行おうとする場合があります。しかし、休息不足は疲労の蓄積だけでなく、怪我のリスクも高めてしまいます。筋肉の回復には、一般的に48~72時間程度が必要とされています。
睡眠も休息の一つです。睡眠中は成長に関わる様々な身体機能が活発になるため、質の良い睡眠を確保するのが推奨されています。一般的に7~8時間程度の睡眠時間を確保することが推奨されることが多いです。
栄養補給のタイミングが適切でない
トレーニングを行う際のエネルギー源となる栄養が不足していると、体が思うように動かず、きついと感じやすくなります。特に、空腹状態でトレーニングを行うと、エネルギー不足により集中力が低下し、パフォーマンスが落ちることがあります。
トレーニング前には、消化の良い炭水化物を中心とした軽食を摂ることで、エネルギーを補給できます。バナナやおにぎりなど、手軽に食べられるものが選択肢の一つです。また、トレーニング後は、たんぱく質と炭水化物を組み合わせて摂取すると、筋肉の回復を促しやすくなります。
水分補給も忘れてはいけません。脱水状態では、パフォーマンスが低下し、疲労を感じやすくなります。トレーニング前後だけでなく、トレーニング中もこまめに水分を補給しましょう。
フォームが正しくない
正しいフォームでトレーニングを行わないと、狙った筋肉に適切に負荷がかからず、他の部位に余計な負担がかかってしまいます。これにより、本来よりもきつく感じたり、思うような変化が得られなかったりすることがあります。
例えば、スクワットで膝が内側に入ってしまったり、背中が丸まってしまったりすると、膝や腰に過度な負担がかかります。ベンチプレスで肩甲骨を適切に寄せられていないと、肩に余計な負担がかかり、胸の筋肉を十分に使えません。
正しいフォームを身につけるには、最初は軽い重量や自重で練習しましょう。鏡を見ながら動作を確認したり、可能であれば経験者にフォームをチェックしてもらったりすれば、徐々に正しい動作を習得できます。フォームが安定してから、少しずつ負荷を上げていくことで、安全にトレーニングを続けられます。
目標設定が現実的でない
「1ヶ月で10kg減量する」「すぐに筋肉をつけたい」といった短期間での変化を期待すると、現実とのギャップに苦しむことになります。体の変化には時間がかかるものであり、過度な期待は挫折の原因となってしまいます。
筋肉の成長や体脂肪の減少は、個人差はあるものの、一般的に数ヶ月単位の時間が必要です。
現実的な目標設定のためには、小さな目標を積み重ねていくことが推奨されています。例えば、「今月は週2回のトレーニングを継続する」「来月は扱える重量を2.5kg増やす」といった達成可能な目標を設定することで、モチベーションを維持しやすくなります。
きつい筋トレを乗り越える実践的な方法
筋トレがきついと感じる理由を理解したら、次は具体的な対処法を実践していきましょう。ここでは、すぐに取り入れられる実践的な方法を紹介します。
トレーニング強度の調整方法
トレーニング強度を適切に調整することは、きつさを軽減しながら継続するためのポイントです。段階的に負荷を増やしていく「漸進性の原則」に従って、無理のない範囲で少しずつ強度を上げていきます。
初心者の方は、まず自重トレーニングから始めるのも選択肢の一つです。腕立て伏せ、スクワット、プランクなどの基本的な種目で、正しいフォームを身につけながら基礎体力を向上させていきます。自重トレーニングでも、回数や動作のスピードを調整すれば、強度を変えられます。
慣れてきたら、ダンベルやバーベルなどの器具を使用したトレーニングに移行していきます。重量を増やす際は、一度に大きく増やすのではなく、2.5kg~5kg程度ずつ段階的に増やしていきましょう。
適切な休息日の設定
トレーニングを継続的に行ううえで、休息日を設けることはパフォーマンス維持と疲労回避に役立つ重要な要素とされています。部位ごとに休息の目安を意識することで、無理なく習慣化しやすくなります。
胸・背中・脚などの大きな筋肉(大筋群)を鍛えた後は、48~72時間程度の休息を取ると良いとされています。一方で、腕・肩・腹筋などの比較的小さな筋肉(小筋群)は、24~48時間程度で回復する場合もあるといわれています。
ただし、これはあくまで目安の範囲であり、トレーニングの強度や時間、個人の回復力、睡眠や栄養状態によって必要な休息時間は異なります。体調を確認しながら、無理のないペースで調整することが大切です。
また、完全な休養日だけでなく、「アクティブレスト(積極的休養)」を取り入れるのも一つの方法です。アクティブレストとは、軽めのウォーキングやストレッチ、ヨガ、サイクリングなどの低強度の運動を行うことで、血流を促し、体のリカバリーをサポートする休息方法のことを指します。
一例としては、
- 月曜日:上半身のトレーニング
- 水曜日:下半身のトレーニング
- 金曜日:全身のトレーニング
とし、他の日を休息またはアクティブレストに充てるなど、週単位でバランスを取るスケジュールも考えられます。
自分の生活リズムや疲労の状態に合わせて、継続しやすいサイクルを見つけることがポイントです。
モチベーション維持のテクニック
筋トレを継続するためには、モチベーションを維持することが不可欠です。小さな成功体験を積み重ねることで、トレーニングへの意欲を保ちやすくなります。
トレーニング記録をつけると、モチベーション維持に役立ちます。扱った重量、回数、セット数、体調などを記録することで、自分の成長を可視化できます。スマートフォンのアプリや手帳を活用して、簡単に記録を残せる方法を見つけましょう。
継続のための工夫として、以下のような方法があります:
- トレーニング仲間を見つけて一緒に取り組む
- 好きな音楽を聴きながらトレーニングする
- トレーニング後の楽しみを設定する(好きな飲み物を飲む、など)
- 達成した目標に対して自分へのご褒美を用意する
- トレーニングウェアなど、お気に入りのアイテムを揃える
- 定期的に体の写真を撮影して変化を記録する
また、完璧を求めすぎないのも大切なポイントです。体調が優れない日や忙しい日は、軽めのトレーニングにしたり、休息日にしたりと柔軟に対応すれば、長期的な継続につながります。
筋トレの頻度と強度の目安
適切な頻度と強度でトレーニングを行うことで、きつさを感じにくくしながら、体力を向上させることができます。自分のレベルに合わせた設定が大切です。
初心者向けの頻度設定
初心者の方は、週2~3回のトレーニングから始めるのが選択肢の一つです。この頻度であれば、十分な休息を取りながら、運動習慣を身につけられます。
最初の1~2ヶ月は、全身をまんべんなくトレーニングする「全身法」で行います。1回のトレーニングで、胸、背中、脚、腕、肩、腹筋など、主要な筋肉グループを一通りトレーニングします。各部位1~2種目ずつ、合計6~8種目程度に抑えることで、疲労を溜めすぎずに済みます。
慣れてきたら、徐々にトレーニング日数を増やしたり、種目数を増やしたりしていきます。ただし、急激な変化は避け、2~3週間ごとに少しずつ調整していくのが推奨されています。体の反応を見ながら、無理のない範囲で進めていきましょう。
中級者以降の取り組み方
トレーニングに慣れてきた中級者以降は、「分割法」を導入することで、より集中的に各部位をトレーニングできるようになります。分割法とは、日によってトレーニングする部位を分ける方法です。
例えば、2分割法では、上半身と下半身を別の日にトレーニングします。3分割法では、「胸・三頭筋」「背中・二頭筋」「脚・肩」といった組み合わせで分けられます。各部位により多くの種目と時間をかけられるため、筋肉への刺激を増やせます。
| レベル | 週あたりの頻度 | トレーニング方法 | 1回の所要時間 |
| 初心者 | 2~3回 | 全身法 | 30~45分 |
| 初級者 | 3~4回 | 全身法または2分割法 | 45~60分 |
| 中級者 | 4~5回 | 2~3分割法 | 60~75分 |
| 上級者 | 5~6回 | 3~4分割法 | 75~90分 |
強度と頻度のバランスを取るのも大切なポイントです。高強度のトレーニングを行った日の翌日は、低強度にしたり休息日にしたりすることで、オーバートレーニングを防げます。また、定期的に「ディロード週」を設けて、通常の60~70%程度の強度でトレーニングを行う週を作ることで、蓄積した疲労を回復させられます。
きつさを感じにくくする筋トレメニューの組み方
トレーニングメニューの組み方を工夫することで、同じ運動量でもきつさを感じにくくなります。ウォーミングアップからクールダウンまで、各段階で適切な方法を取り入れていきましょう。
ウォーミングアップの重要性
ウォーミングアップは、体温を上昇させ、筋肉や関節の動きを良くすることで、本番のトレーニングに備える準備運動です。適切なウォーミングアップにより、怪我のリスクを減らし、パフォーマンスの向上が期待できます。
ウォーミングアップは、5~10分程度の軽い有酸素運動から始めます。トレッドミルでのウォーキングなど、全身を使う運動で心拍数を徐々に上げていきます。その後、動的ストレッチを行います。動的ストレッチとは、体を動かしながら行うストレッチのことで、腕回しや脚振り、体幹のひねりなどがあります。
トレーニングする部位に応じた特異的なウォーミングアップも推奨されています。例えば、ベンチプレスを行う前には、軽い重量で10~15回程度の動作を行い、筋肉と神経の連携を高めます。このような準備により、本番のセットで力を発揮しやすくなります。
種目の順番と組み合わせ
トレーニング種目の順番を適切に組むことで、疲労を分散させ、きつさを軽減できます。基本的には、大筋群から小筋群、複合種目から単関節種目の順番で行います。
大筋群(胸、背中、脚)のトレーニングは、多くのエネルギーを必要とするため、体力がある序盤に行います。その後、小筋群(腕、肩)のトレーニングを行うことで、全身をトレーニングできます。
複合種目(スクワット、デッドリフト、ベンチプレスなど)は、複数の関節と筋肉を同時に使う種目で、高い集中力が必要です。これらを先に行い、その後に単関節種目(アームカール、レッグエクステンションなど)を行うことで、安全にトレーニングを進められます。
種目間の休息時間も考慮すべきポイントです。複合種目や高強度のトレーニング後は2~3分、単関節種目や低強度のトレーニング後は1~2分程度の休息を取ることで、次のセットで適切なパフォーマンスを発揮できます。
クールダウンとストレッチ
トレーニング後のクールダウンは、心拍数を徐々に下げ、筋肉の緊張を和らげる時間です。5~10分程度の軽い有酸素運動を行い、その後静的ストレッチを行います。
静的ストレッチは、一定の姿勢を15~30秒程度保持するストレッチです。トレーニングで使った筋肉を中心に、ゆっくりと伸ばしていきます。痛みを感じない範囲で、心地よい伸び感を感じる程度に行いましょう。
クールダウンを適切に行うことで、翌日の筋肉痛を軽減し、疲労回復を促進しやすくなります。また、柔軟性の維持・向上にもつながり、怪我の予防にも役立ちます。時間がない日でも、最低限のストレッチは行うようにしましょう。
筋トレがきつい時期を乗り越えた後の変化
筋トレがきついと感じる時期を乗り越えて継続していくと、様々な変化を実感できるようになります。これらの変化を知ることで、モチベーションの維持にもつながります。
体力面での変化
継続的な筋トレにより、日常生活での疲れにくさを実感できるケースがあります。階段の上り下りが楽になったり、重い荷物を持つのが苦にならなくなったりといった変化を感じる方もいます。
運動能力の向上も実感しやすい変化の一つです。最初は10回しかできなかった腕立て伏せが20回できるようになったり、扱える重量が増えたりして、自分の成長を実感できます。また、姿勢が良くなったり、体のバランスが改善されたりすることもあります。
そして、睡眠の質が向上する方もいます。適度な運動による心地よい疲労感により、寝つきが良くなったり、深い睡眠を得やすくなったりします。質の良い睡眠は、疲労回復を促進し、翌日のパフォーマンス向上にもつながることもあります。
メンタル面での変化
筋トレの継続により、メンタル面でも様々な変化を感じられるでしょう。目標を設定し、それを達成する経験を積み重ねていくと、自信が向上しやすくなります。
運動後の爽快感や達成感は、ストレス解消にも役立ちます。トレーニング中は集中して体を動かすため、日常の悩みから一時的に離れられます。また、定期的な運動習慣は、生活リズムを整える働きもあり、心身のバランスを保ちやすくなります。
自己管理能力の向上につながるケースも見られます。トレーニングスケジュールの管理、食事への意識、睡眠時間の確保など、健康的な生活習慣が身につくと、全体的な生活の質が向上していきます。
よくある質問
筋トレに関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q1: 筋トレは毎日やってもいいですか?
A: 同じ部位を毎日トレーニングするのは避けた方が良いでしょう。筋肉の回復には時間が必要なため、同じ部位は48~72時間程度の休息を設けるのが推奨されています。
ただし、部位を変えてトレーニングする分割法であれば、毎日異なる部位をトレーニングするという選択肢もあります。初心者の方は、週2~3回から始めて、徐々に頻度を調整していくのも一つの方法です。
Q2: 筋肉痛がある時もトレーニングすべきですか?
A: 強い筋肉痛がある場合は、その部位を休ませましょう。筋肉痛がある部位とは別の部位をトレーニングするか、完全に休息日にすることも選択肢です。痛みが長期間続く場合は、専門家への相談も検討しましょう。
Q3: どれくらいで体の変化を実感できますか?
A: 体の変化を実感するまでの期間は個人差が大きく、トレーニング内容、頻度、食事、睡眠など様々な要因によって左右されます。一般的に、筋力の向上は2~4週間程度で感じられる場合がありますが、見た目の変化には2~3ヶ月程度かかるケースもあります。
変化を期間で期待するのではなく、長期的な視点で取り組みましょう。小さな変化を見逃さず、記録を取りながら継続すれば、成長を実感できるでしょう。
Q4: 年齢によってきつさは変わりますか?
A: 年齢によって体力や回復力に違いがあるため、同じトレーニングでも感じるきつさは変わることがあります。年齢を重ねると、筋肉の回復に時間がかかりやすくなる傾向があるため、休息期間を長めに取るのが推奨されています。
しかし、年齢に関係なく、適切な強度と頻度でトレーニングを行えば、体力の維持・向上は期待できます。自分の体調と相談しながら、無理のない範囲で継続するのが大切です。
まとめ
筋トレがきついと感じるのは、誰もが経験する自然な反応です。その理由を理解し、自分に合った対処法を見つければ、継続しやすくなります。運動強度の調整、適切な休息、栄養補給のタイミング、正しいフォーム、現実的な目標設定など、様々な要素を見直すことで、きつさを軽減しながら継続できるようになります。
トレーニングは、自分のペースで無理なく進めるのが大切です。他人と比較するのではなく、昨日の自分と比較しながら、少しずつ成長していく過程を楽しみましょう。継続により、体力面だけでなくメンタル面でも様々な変化を実感できるはずです。
筋トレは長期的な取り組みです。きつい時期もありますが、それを乗り越えた先には、より健康的で充実した生活が待っています。焦らず、無理をせず、自分のペースで続けていくことで、着実に目標に近づいていけるでしょう。今日から、自分に合った方法で、一歩ずつ前進していきましょう。
※トレーニングや食事管理の効果には個人差があります。本記事は医療行為や医療上の効果を保証するものではありません。
他の記事を読む
 筋トレを何から始めればいい?男性向け基本ガイド
筋トレを何から始めればいい?男性向け基本ガイドトレーニング方法
2025.10.29
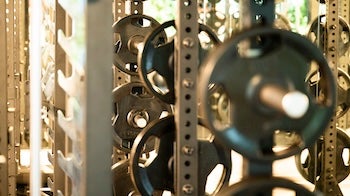 筋トレモチベーションを維持する方法と続けるコツ
筋トレモチベーションを維持する方法と続けるコツトレーニング方法
2025.10.28
 ボディメイクのための筋トレ入門|基礎知識と実践方法
ボディメイクのための筋トレ入門|基礎知識と実践方法ダイエット・ボディメイク
トレーニング方法
2025.10.09
 ジムで行う有酸素運動に向くマシンや取り組み方のポイント
ジムで行う有酸素運動に向くマシンや取り組み方のポイントトレーニング方法
2025.10.06
 ジムで行う体幹トレーニングガイド!マシンの使い方解説
ジムで行う体幹トレーニングガイド!マシンの使い方解説トレーニング方法
2025.10.02
 ジムで行うストレッチのやり方完全ガイド!順番・時間・効果的な方法とは?【2025年版】
ジムで行うストレッチのやり方完全ガイド!順番・時間・効果的な方法とは?【2025年版】トレーニング方法
2025.09.30
カテゴリーから記事を探す
無料カウンセリング
実施中
※無理な勧誘は一切ございません